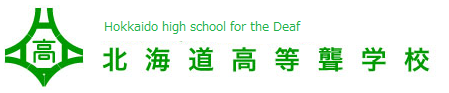今日の高聾
サッカー部 ウェルビーイングフットサルフェスティバル2024大会結果について
昨年12月22日(日)に行われましたウェルビーイングフットサルフェスティバル2024大会結果についてお伝えします。今大会は、全4試合行い、1回戦は豊明高等支援学校OBに2対1、2回戦は札幌NFC(社会人チーム)に8対0、3回戦はみなみの杜高等支援学校に2対1、4回戦は白樺高等養護学校に2対3と3勝1敗という結果でした。フットサルフェスティバルということで、勝敗による順位決定はありませんでしたが、12月8日に行われたフットサル大会の反省を活かし、一人一人が自分の役割に責任をもって試合に臨むことができました。今後も様々な大会に出場し、成長していきたいと考えています。
学びの一年を終えて
12月23日(月)は、2024年の最後の登校日となりました。
今年も生徒・学生の皆さんは日々の学びや活動に励み、それぞれが目標に向かって努力してきたことと思います。
その結果、資格試験に合格したり、大会やコンテストで成果を残したりする等、充実した一年となりました。
冬季休業中も、これまでの学びを大切にしながら、次の目標に向けて計画的に取り組んでください。
また、しっかりと体を休め、新しい年に向けて英気を養ってください。
2024年は、保護者や地域の皆様等、多くの方々にご支援とご協力をいただきました。
2025年も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
▲寄宿舎の前に雪だるまが登場!冬の風景を彩っています
Shiawase cafe OPEN
12月13日(金)13:20 リーダーの「丁寧で笑顔のあふれる接客をしましょう。みんなで協力して頑張りましょう。おー!!」という発声で生徒も教師も心を一つにしてオープンの時間を迎えました。今年はオープン直後より大盛況となり、交流を深めている小樽高等支援学校の生徒さん、重複学級の保護者様、本校生徒や教職員を含め約90名近くのお客様に利用していただきました。
11月から始めた「カフェを開こう」という単元の集大成となり、終わった後のお疲れ様会では、みんなが達成感に満ちた表情を浮かべていました。翌週の反省会では自分の目標に対する反省や次年度に向けての意気込みを発表しました。1・2年生は、「次年度もカフェをやりたい!」という気持ちを。3年生は「来年も自分たちがやってきた接客(動き方)を続けて欲しい。」という気持ちを後輩に伝えていました。この学習活動を通して学んだことや自分の良さや強みを、これからの学習活動に生かして欲しいと感じています。
今後のHP更新もお楽しみに!!
Shiawase cafe
「笑顔で接客しましょう!えい、えい、おー!!」
開店と同時に大盛況です!!
リーダーが始めたお客様への椅子引きサービスはとても喜ばれました。
今年は生徒がデザインしたイラストを使ってTシャツを作りました。
笑顔や姿勢に練習の成果が見られます。
お客様の会話も弾みます。
アンケートより…
「接客がとても丁寧で素晴らしかったです。」
「たくさん練習した様子が伝わり、幸せな気持ちになりました。」
「おしゃれな雰囲気が良くて、とてもゆったりと過ごせました。」
令和6年度第7回北海道高等聾学校スポーツ大会
12月21日(木)、本校体育館で令和6年度第7回北海道高等聾学校スポーツ大会が実施され、「バレーボール」、「ボッチャ」、「モルック」の3つの競技を行いました。
生徒たちの互いに声を掛け合いながら、最後まで全力で取り組む姿が印象的でした。
特に学年対抗のバレーボールでは、接戦が続き、会場は熱気に包まれ、大いに盛り上がりました。


全校朝会・表彰伝達式
12月12日(木)に、本校で全校朝会と表彰伝達式が行われました。
表彰伝達式では、美術部の生徒の入展やさまざまな資格試験で成果を挙げた生徒たちが表彰されました。それぞれが日々の努力を重ねた結果が認められたものであり、その成果を大変誇りに思います。
校長先生からのお話では、「自分を知ること」についてのお話がありました。「自分を知ること」は、「自己モニター」や「自己コントロール」と深い関係があり、自分の考えや行動を振り返り、より良い選択をするために大切な力です。校長先生のお話に学び、生徒の皆さん一人ひとりがこれからの成長につなげていくことを期待しています。

普通科重複学級「Shiawase Cafeプレオープン」
12月3日(火)に北海道小樽高等支援学校福祉サービス科1年生をShiawase Cafeにお客様としてお招きしました。本校と小樽高等支援学校は「お隣さん」と表現することもあるくらい距離が近く、Shiawase Cafeを始めた昨年度より、お隣のカフェ「ポッポリー」を利用しながら接客について勉強させていただいています。その成果を発揮すべくプレオープンでは、本校の生徒が接客をし、交流会でご意見をいただきました。交流会での貴重なご意見を胸に、本番に向けての再調整をしているところです。
本番の様子についてもHPでの更新をお楽しみに!

サッカー部 第24回 北海道チャレンジドフットサル大会の結果
第24回北海道チャレンジドフットサル大会がつどーむで行われました。
予選リーグでは、みなみの杜高等支援学校に0対1、中札内高等養護学校に1対1、美深高等養護学校に1対0と1勝1敗1分けと3位になりました。他ブロックとの3位同士の試合では、函館五稜郭FCに4対0で勝利することができました。「しっかり守って勝つ」というチームでの約束事も、最少失点という結果で表すことができました。
次は12月22日(日)年内最後大会があるので、また頑張ります。
寄宿舎 よつば会選挙
12月5日(木)、よつば会選挙を行いました。
男子ブロックと女子ブロックの代表者を決める重要な選挙です。全員真剣に演説を聞いていました。
生徒たちは皆、自分たちの生活に直接関わる選挙であることを意識し、清き一票を投票しました。
普通科重複学級「Shiawase Cafeに向けた学習」
重複学級では12月13日に行われるShiawase Cafe(しあわせカフェ)に向けた学習をしています。
会場に飾る大きいのぼりやテーブル用の小さいのぼり制作、飲み物と一緒に食べていただくクッキーの試作、美味しいコーヒーの入れ方、お客様対応の接客練習などを学習しています。


クッキーの試作では、最初に話し合いで形や味は何が良いか決めてから、グループで分担してクッキー作りを行い、試食して味を確認しました。
接客練習では、お客様を座席に案内することから片付けまでを丁寧かつスムーズにできるように練習をしています。昨年のカフェを経験している上級生は、案内・提供・片付けの一連の流れが上手く、1年生の見本になる動きを見せてくれています。カフェ初体験の1年生は動きがわからなくて立ち止まってしまうこともありますが、次は何をするのか確認しながら取り組んでいます。
13日の本番に向けてさらに良くなるように練習を頑張ります。


第72回小樽地区高校秋季バドミントン選手権大会(バドミントン部)
11月16日小樽潮陵高校にて男子と女子のダブルス戦とシングルス戦、23日余市町総合体育館にて男子団体戦が行われました。
本校からはバドミントン部8名の選手が参加しました。
試合結果は以下の通りです。
11月16日
<男子ダブルス>
1回戦敗退(2組)
<男子シングルス>
1回戦勝利-2回戦敗退(1名)
1回戦敗退(4名)
<女子シングルス>
1回戦勝利-2回戦敗退(1名)
1回戦敗退(2名)
11月23日
<男子団体戦>
1回戦敗退
敗者戦敗退


ほっこりふれあいプロジェクトに参加(クリーニング科)
11月15日、18日と北海道庁で開催された「ほっこりふれあいプロジェクト」に今年度初めて参加してきました。会場では、道立の特別支援学校の特色ある教育活動の紹介や実演、販売が行われ、クリーニング科では授業の様子をまとめたポスターや実際に使っている道具、キレイに仕上げたワイシャツの展示と生徒が実際にスチームアイロンを使って来場者のジャケットやコートのシワを伸ばす実演をしてきました。多くの方に利用していただき、喜んでいただくことができました。
日頃の学習の成果を発揮し、他校の取り組みを知り、生徒間の交流ができた貴重な経験となりました。


就業体験発表会(1学年)
11月14日と18日の2回にわたり、1学年の生徒による就業体験発表会が開催されました。
生徒たちは、10月21日から25日まで行われた就業体験を通して得た学びをPowerPointにまとめ、コンピュータ操作も自ら行いながら発表しました。
発表の中では、「丁寧にやり遂げる責任を感じた」「これまではお客様の立場だったが、接客の苦労を体験し、新しい視点を得た」といった気づきや、「積極的に質問できなかったことから力不足を痛感した」「挨拶を含む職場でのコミュニケーションの大切さを改めて感じた」などの具体的な経験が語られました。
仕事を通じた学びが将来への意欲につながる様子が伝わってきました。
今後は、個々の課題について、具体的な取り組みを面談しながら話し合って行く予定です。
実り多き、就業体験でした。
各種証明書の発行について(更新)
「各種証明書の発行について」のページが更新されました。
意見発表会
本日、本校で「意見発表会」が開催されました。
生徒たちは、自分の意見を堂々と発表し、多くの観客の前で緊張しながらも、
伝えたいという強い意志を持って取り組む姿が印象的でした。
この会を通じて、生徒たちは自分の考えをまとめ、伝える力を磨く貴重な経験を積むことができました。
聞いている生徒や先生方も集中して発表に耳を傾けていました。

2学年 見学旅行
2学年は10月29日(火)から11月1日(金)まで関西地域への見学旅行を実施しました。
生徒たちは北海道とは異なる風土・歴史に触れ、多くのことを学んだ様子でした。
また、班ごとの自主研修を通じて、仲間との絆を深めることができました。
見学旅行での経験を今後の学校生活に生かしてくれることを期待しています。
本旅行の実施にあたり、多くの方々からご尽力とご協力をいただきました。
事故もなく無事に終えることができましたこと心より感謝申し上げます。
【日程概要】
1日目:奈良公園、東大寺
2日目:自主研修(清水寺、金閣寺、道頓堀など)
3日目:USJ
4日目:新千歳空港へ帰着
初雪の便り
本日、本校では今年初めての雪が降り、校舎の周辺がうっすらと白く染まりました。
冬の訪れを感じさせる景色が広がり、生徒たちも驚きの声を上げています。
雪に包まれた校舎の様子です。

陰で支える生徒たち~意見発表会の舞台裏~
11/8(金)に本校で予定されている「意見発表会」に向け、生徒たちは準備に励んでいました。
放課後の時間を使い、生徒たちは冊子の制作から会場の設営まで中心となって取り組んできました。
体育館では、司会者やタイムキーパーが入念なリハーサルを行っていました。
当日は、発表者がメインとなりますが、裏方としてサポートに徹する生徒たちの姿も見逃せません。
発表者だけでなく、多くの生徒が協力し合い、素晴らしい発表会にしてほしいと思います。
普通科重複学級「作業学習A コースター制作」
普通科重複学級の作業学習Aの革工ではコースター制作に取り組みました。
教職員向けに販売のお知らせをしたところ、32枚の注文がありました!
“心をこめてコースターを作ろう”を合い言葉に一つ一つ丁寧に作りました。
最終作業、完成に向けて頑張りました。ラッピングも協力しながら取り組みました。

(床磨き・コバ磨きの様子) (ステッチングの様子)

(ラッピングの様子) (完成したコースター)
「協力して作りました。」「長く大切に使ってもらえると嬉しいです。」などの言葉を添えて、
注文していただいた方の顔をしっかり見て、手渡すことができました!


普通科重複学級「作業学習B 紙すき」
作業学習Bでは、紙すき作業をしています。
ミキサーで攪拌したパルプ液を木枠に流し込むときに紙の厚みが偏らないようにバランスよく流したり、ローラー掛けの力加減を意識したりと手順表を見ながら作成しています。
ここで作られた紙を12月に行われる Shiawase Cafe(しあわせカフェ)でチケットやメニュー表として使用します。
<紙すき作業の手順>
細かく裁断された紙を決められた量を計り、水と一緒にミキサーに入れて攪拌しパルプ液を作ります。


偏らないようにタテヨコに揺らしながらバランスよく木枠に流し、ゴミが入っていないか確認します。

水抜きと薄くのばすために力加減を変えて何度かローラーを掛けます。

乾燥させて完成です。
校舎周辺に広がる秋の風景
朝晩の冷え込みが増し、学校の周りは秋の風景が広がりつつあります。
木々が色づき始め、葉が赤や黄色に染まる様子は、まさに秋の風物詩です。
昼休みには、秋の風景を撮影している生徒の姿も見かけました。
そんな生徒の様子からも、秋の訪れを楽しんでいるのが伝わってきます。
本校美術部生徒による作品が「小樽ユース展」において展示されます
令和6年10月30日(水)から11月3日(日)まで、小樽市文化祭のコンテンツの一部として、市立小樽美術館市民ギャラリーにおいて「小樽ユース展」が開催されています。地域の高校生等による感性豊かな作品が集まるこの展覧会に、本校美術部の生徒も作品を出品しています。
今回の展示では、昨年度の高文連大会や北海道美術協会主催「道展21」への出品実績のある作品も含まれています。
今回の小樽ユース展出品作品は、これまでの成果の集大成的な意味も込められています。これまでの活動経過を作品をとおして発表する場でもあり、若い感性だからこそ表現できる斬新なアイデアや感情の揺らぎが込められた作品が、訪れる人々に強い印象を与えるものと確信しています。
「小樽ユース展」は11月3日(日)まで開催されており、どなたでも無料で観覧可能です。もし機会がございましたら、足を運んでみていただければと存じます。
開催期間:令和6年10月30日(水)~11月3日(日)
会場:市立小樽美術館 市民ギャラリー
観覧料:無料
令和6年度第75回小樽市文化祭 特設ページ
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2024061200030/
生活情報科のページが更新されました
生活情報科のページが更新されました。
生活情報科のページ からご覧ください。
12月行事予定
「12月行事予定」を公開しました。
行事予定のページ から参照ください。
第36回有島武郎青少年公募絵画展で美術部所属生徒作品が審査員特別賞を受賞
ニセコ町で2024年10月26日から行われる「第36回有島武郎青少年公募絵画展」に本校美術部からも作品を出品しておりましたが、1年生の生徒が制作した作品が「審査員特別賞」を受賞しました。これは、歴代の美術部においても、奨励賞以上の受賞は初となります。
また、その他の1年生から3年生までの部員4名が入選いたしました。
競争率の高い公募展であり、全体に作品の質も非常に高いのが特徴となっていますが、美術部所属生徒が入選のために各人の工夫を凝らしつつ、「自分の表現したいものを表現する」というクリエイティブの本質を失わずに制作を進めてきたこれまでの活動の成果が現前したのだと思います。素晴らしいです。
「第36回有島武郎青少年公募絵画展」は、2024年10月26日(土)~11月10日(日)まで、ニセコ町の有島記念館で行われます。
◎「第36回 有島武郎青少年公募絵画展」特設ページ
https://www.town.niseko.lg.jp/arishima_museum/kikaku/kikaku_2024/10879/
就業体験の事前準備(1学年)
来週から始まる就業体験に向けて、1学年の生徒たちは事前準備を進めています。
インターネットを活用して、実習先の情報や交通手段を確認したり、挨拶の練習をしたりするなど、実習に向けた学習に熱心に取り組んでいました。事前の挨拶に行く前は、「迷惑をかけたらどうしよう」、「コミュニケーションが不安」といった声がありましたが、
実際に訪れてみると「優しそうな人で安心した」、「来週から頑張ろう」という声が聞こえ、生徒たちが意欲的に取り組もうとしている様子が見られました。
生徒一人一人がこの体験を通して成長し、多くのことを学んでくれることを期待しています。
重複学級 校外学習
10月1日(火)に新札幌へ行ってきました。
始めに行った倉式珈琲店では、12月に行うShiawase Cafeに向けて、実際のお店では店員がどのように働いているか見ながらドリンクやデザートを飲食してきました。
青少年科学館では体験活動を通して学習し、理科の授業から出ていた課題のカーリング体験やスケルトン体験、ぐにぐにミラーでの写真撮影などに取り組むことができました。
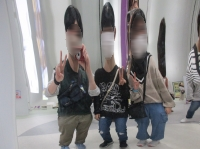

昼食と自主研修をグループで行いました。事前学習で考えた行きたい店や見学したい場所を、予定通りの順番で回ることができました。
帰校後の振り返りでは「初めてプリクラをとりました。」「海鮮丼が美味しかったです。」「サイゼリヤで食べた昼食は美味しかったです。また行きたいです。」「女子四人で仲良く、自主研修をしました。楽しかったです。」という感想が聞かれました。

生徒会役員認定式
本日、「生徒会役員認定式」が行われました。
式では、校長先生より新たな生徒会役員への認定証の授与が行われました。
新生徒会長の挨拶では、生徒一人ひとりが気軽に声をかけてくれるような存在でありたいと語り、学校全体をより活気あふれる場にしていくという意気込みを述べました。
新しい生徒会役員の皆さんが、これからの学校生活をさらに豊かにしてくれることを期待しています。
美術部が高文連全道大会に参加、1名が全道優秀作品に推挙されました
10月9日(水)と10日(木)の二日間、旭川市大雪アリーナで開催された高文連美術専門部の全道大会(旭川大会)に参加させていただきました。この大会には、地区大会で全道推薦作品に推挙された3名と、佳作入選の1名、計4人が参加しております。
加えて、全道推薦を受けた3つの作品のうち1点が全部優秀作品に選出されました。非常に光栄なことであるとともに、他に代えがたい成果を収めることができたと考えております。また、この結果は、日頃の努力の結晶であり、他の参加メンバーにとっても大きな励みとなったものと考えます。
大会会場では、全国各地から集まった地区大会を勝ち抜いた優秀な作品が並び、部員がそれぞれの課題に応じつつも、そのクオリティの高さに感銘を受けました。参加者にとっても、作品を通じて切磋琢磨する場となり、互いに刺激を受けながら充実した時間を過ごすことができたと思われます。
また、大会期間中には旭山動物園でのスケッチ研修も行われました。各メンバーが興味を持った動物の前で、思い思いにスケッチを描くという内容であり、それなりに創造性を深める貴重な体験とはなっていたようです。
今回の大会参加を通じて、作品制作における問題意識と当事者意識を高めつつある中で、全道大会レベルの質的に高い作品に触れることで、自己と他者を相対的に見る視点を養い、今後の創作活動に向けた重要な気づきを得ることができたと感じています。この経験を活かし、さらに高次元化された作品制作に進むことができればと考えます。
表彰伝達式・後期始業式
本日、表彰伝達式及び後期始業式が行われました。
表彰伝達式では、検定試験や大会で優れた成績を収めた生徒たちが表彰されました。
日々の努力が実を結び、その成果が現れたことを誇りに思います。
後期も、引き続き努力と挑戦を続け、生徒・学生たちが成長することを期待しています。

生徒会役員選挙
9月26日(木)に、生徒会役員選挙が行われました。 立候補者たちは、生徒の代表としての意欲を持ち、目標や考えをしっかりと発表しました。 また、他の生徒たちも真剣に聞いていました。 認定式は、10月7日に行われる予定です。
寄宿舎 どんどこ会
10月3日(木)寄宿舎生の交流を深める行事「どんどこ会」がありました。この行事は、男女ブロック長と2学年の舎生が実行委員となり、7月下旬から準備を進めてきました。
当日、会場係が作成した装飾物でハロウィンの雰囲気に包まれた食堂で、おしゃれをして集合する舎生達の中にテーマに合わせて仮装をして参加する舎生もおり、楽しい雰囲気で会が始まりました。
舎生のリクエストが反映された豪華な夕食と、余興係が「みんなに楽しんでほしい。」と真剣に考えた余興で楽しい時間はあっという間に過ぎました。最後に仮装大賞の発表と集合写真を撮影し、会は終了となりました。
11月行事予定
「11月行事予定」を公開しました。
行事予定のページ から参照ください。
9月29日(日)に桂岡町内会「防災ウォーク2024」に参加しました
当日在舎している生徒・学生とともに、地域の防災活動に参加をしてきました。
会館から桂岡小までの模擬避難、段ボールベットづくり、備蓄品保管状況の見学、災害食や炊き出しの試食などから、参加者各々に避難行動や地域の方々の中での避難生活にイメージをもつことができました。また、講演では「自助(自分で)・共助(地域で)・公助(自治体で)」の話を伺いました。自治体等から食べ物が届くまでに数日ほどかかると想定する必要があること、自助・共助が非常に重要であることについて学びました。自分ごととして学ぶよい機会となりました。
普通科重複学級「作業学習」
普通科重複学級の作業学習で革の加工実習をスタートさせました。今年度初めての取り組みとなりますが、革のコースターを制作しています。コースター制作の流れは、革の裁断、ステッチンググルーバー、菱目打ち、ステッチング、床磨き、コバ磨き、仕上げ磨きと工程はたくさんあります。全ての工程をまずは一通り経験してから、本人の希望を聞いたり、得手不得手を見極めたりして作業分担をしています。自分が担当した作業を終えると次の担当へ「おねがいします」と手渡し、みんなで力を合わせて1枚のコースターを完成させます。今年度は、校内にて数量限定で受注販売をさせていただきました。たくさんの方にご賛同いただき、あっという間に完売となりました。一つ一つ丁寧に仕事をして、注文いただいたお客様に喜んでもらえるコースターを作っていきます。
菱目打ち↓ ステッチング↓


第2回 避難訓練
9月12日、今年度2回目の避難訓練を行いました。火災を想定した訓練で、生徒・学生達は緊張感を持ちつつも落ち着いた足取りで避難をしていました。
この訓練を通じて、万が一の災害に備える大切さを再確認し、防災意識を高めることができました。
今後も日頃からの備えと対応力を身に付けて欲しいと思います。
クリーニング科 学科だより第4号
クリーニング科 学科だより(学科通信ピカピカcleaning4号)が公開されました。
クリーニング科のページ からご覧ください。
卒業生体験講話
9月13日(金)に本校で「卒業生体験講話」が行われました。大橋由佳氏を講師にお迎えし、「企業で働くということ 社会人として後輩に伝えたいこと」をテーマにお話しいただきました。
大橋氏は令和3年度に本校普通科を卒業し、現在は株式会社豊田自動織機に勤務されています。講演では、職場での具体的なエピソードを交え、社会人としての心得や就労の現実について在校生に語られました。
また、在学中の進路選択の過程についても触れ、在校生が自身の将来を考えるための貴重なアドバイスがありました。
この講話を通して、生徒たちは進路についてさらに考えを深める機会となりました。今後の目標に向けて積極的に取り組んでいってほしいと思います。
第23回北海道チャレンジドサッカー大会(8人制)
サッカー部大会結果についてお伝えします。
第23回北海道チャレンジドサッカー大会(8人制)が9月16日(月)に栗山町ふじスポーツ広場で行われました。
今大会は、北海道小樽高等支援学校サッカー部との合同チームで出場し、選手同士の顔合わせやフォーメーション等、事前の合同練習で確認してから挑みました。
予選リーグでは、1勝2敗で3位となり、順位決定戦では社会人チームに善戦しましたが、1対2で敗戦しました。全7チーム中、6位という順位でしたが、生徒同士の交流も見られとてもいい経験になったと思います。
今後も交流を深めながら、活動していきたいと思います。
10月行事予定
「10月行事予定」を公開しました。
行事予定のページ から参照ください。
産業技術科の生徒たちがトレース技能検定模擬試験に挑戦!
9月4日から6日までの3日間、高等聾学校の産業技術科の2学年と3学年の生徒たちがトレース技能検定模擬試験に挑戦しました。本試験は10月16日から予定されており、その先駆けとなりました。この試験は、本試験と同様、理論試験と実技試験の2部構成で行われ、日頃の学習の成果を試す場となりました。
試験が始まる直前まで、生徒たちは熱心に勉強し、真剣な表情で試験に臨んでいました。これからも彼らの努力が実を結び、さらなる成長を遂げていくことを期待しています。
小野寺眞悟杯北海道特別支援学校フットサル大会(サッカー部)
7月27日(土)に、小野寺眞悟杯北海道特別支援学校フットサル大会が行われました。大会の結果は、全18チーム中5位でした。予選リーグでは、6チーム中2位通過になり、同リーグで戦った前年度優勝校の「市立札幌みなみの杜高等支援学校」とは1対1でした。予選・順位決定戦全7試合行いましたが、2勝1敗4分けと善戦しました。次の大会に向けてまた頑張っていきたいと思います。
クリーニング科学科紹介が更新されました
クリーニング科学科紹介が更新されました。
クリーニング科のページ からご覧ください。
高等学校新人陸上競技大会(小樽支部)
8月24日(土)~25日(日)に、小樽支部高等学校新人陸上競技大会が行われました。
本校から陸上部の生徒が出場しました。
全員全力をつくし、良い経験になりました。
出場種目は以下の通りです。
男子100m走:1名
男子6kg砲丸投げ:1名(優勝,全道大会出場権獲得)
男子5000m走:1名(自己新記録)
次の全道大会(9月17日~20日)に向けて、今後も練習に励みたいと思います。
高文連後志地区大会で美術部生徒3名の作品が全道推薦
9月28日から30日の間、市立小樽美術館で行われた高文連後志地区美術専門部の研究大会において3年生2名、2年生1名が全道推薦、2年生1名が佳作に入選となりました。
この4名が10月の旭川で開催される全道大会出場する予定です。
また、3年生の作品については、本校生徒作品が生徒投票では、得票数1位となりました。各校美術部顧問による作品選出においても、本校1年生の作品が選ばれ、全体に紹介いただきました。
本大会の参加作品の多くはファインアートですから、自分の思想信条の表現である以上、自分の作りたいものを表出することが最も大事なことであり、その観点で言えば、作品の優劣はつけがたいものがあります。
他方、本大会は研究大会であり、美術を研究対象として系統的な学びを展開しようとしています。
つまり、「こう描きさえすれば、ある一定のこういう効果がある」「こういう作家の心の動き方にはこういう意味がある可能性が高い」といった、法則性や真理の追求といった側面が本大会にはあり、それは次代に残しえる価値となりうるかどうかとか、全体にとっての価値になるかどうか、といった観点が生まれてくることになります。
本大会は、参加各校の特色が発揮され、非常に内容の濃い、充実した研究活動が行われた大会だったと思います。本校生徒にとっても、半年間の制作活動の評価となりますから、それなりの緊張感もあったと思いますし、校内では得難い価値の伴った活動になったのではないかと思います。
また、本校は特別支援学校であり、高等学校等との交流学習も行事計画にいくつか位置づいていますが、大会では他校の作品への批評(相互批評)は、間接的でありますが、そのような側面も持っていたように感じられました。何かしらの直接的な対面活動はないにしても、質の高い作品及びその批評等を通した間接的交流は、指導上の環境整備が整っていれば、深いレベルでの心情的交流が追及でき、「交流学習」として十分成立しうるものと感心させられました。
クリーニング科のページが更新されました
クリーニング科のページが更新されました。
学科・寄宿舎のページ からご覧ください。
重複学級「発表会」
7月25日(木)に重複学級で「宿泊研修の思い出と就業体験のまとめ発表会」を行いました。
今年度の重複学級の情報の授業では、ICTを活用しGoogleクラスルーム、ドキュメント、スライドを使った学習に取り組んでいます。
発表会に向け、1年生は宿泊研修、2・3年生は就業体験についてスライドを使って、宿泊研修先や就業体験先、それぞれが取り組んだことや感想をまとめました。
発表会では多くの先生方が見ているので緊張した様子が見られましたが、補足説明も入れながら上手に発表し、発表後の質問にも慌てることなく答えていました。
今後もICTを活用した資料の作成と発表の経験を積み重ねていければと思います。

▲発表会の司会進行は3年生が勤めました。


▲それぞれが作った資料を使い発表しました。
▲質疑応答にも立派に対応しました。
▲校長先生が発表会を見にきてくれて「1年生は宿泊研修で仲が良くなったことが伝わってきました」「2・3年生は就業体験で学んだことを日々の生活でも生かしてください」と講評をいただきました。
教育相談
「教育相談」のページが更新されました。
教育相談のページ から参照ください。
9月行事予定
「9月行事予定」を公開しました。
行事予定のページ から参照ください。
令和6年度一般救急講習
本校職員を対象とした標記の講習会が7月30日に行われ、小樽消防署を招聘したAEDを使用した救命措置等についての訓練を行いました。
緊急時の対応は、どうしても音声情報中心となりがちです。例えば、電車乗車中の緊急停車や到着時刻遅れの放送なども、たいていは音声情報になります。車内のディスプレイに表示される情報は、たいてい非常に限定的で定型的な情報であり、必ずしも今、すごそこで起こっていることについて実況する情報が視覚化されるわけではありません。
ですから、今目の前に人が倒れたときの対応も、相当な範囲が音声情報に依存することになります。周囲に声を掛ける、AEDを持ってきてもらう、119番に電話連絡する‥
このような緊急時において聴覚障がいの方が向き合うことになる現実に聴者側が目を向けるといった意味でも、今回の研修は非常に良い機会になるはずです。
また、今回の研修では、聴覚に障がいのある職員も参加しており、研修担当や校長が手話通訳等の情報保障を行っています。聴者中心に構成された社会環境における緊急時への対応には、改めて難しさもあるわけですが、当事者自身も含めてその難しさについて客観的に知り、その上で可能である具体的な対応を考えていく(電話連絡と胸部圧迫の役割を交換することを要請できる、といった)という観点は重要だと考えます。改めて、本校における職員の研修体制においては、聴覚障がいのある職員も多く在籍することを前提とし、必要な環境整備と合理的配慮ができる体制を常に構築できるようにしていかなければなりません。そういう気づきを得る機会としても、非常に重要な機会であったと考えます。
夏期休業手話特別研修
本校では、生徒が不在の長期休業期間、一定のまとまった時間が確保しやすいことから、日本手話ネイティブのろう者で、かつ、専門の指導技術講習を受けられた外部講師を招聘しての手話研修を例年行っています。今年度も夏季休業時の研修を7月30日に行いました。
日常的に手話の研修は、短時間を繰り返す構成で行っていますが、長期休業中の研修では、日本手話の文法事項の中でも聴者にとって習得しづらい要素であるNMM(Non Manual Markers)やCL(classifier)を中心に学習します。今年度、新たに異動された職員にとっては始めて触れる話も多くあり、なかなか刺激的な内容になったようです。
この研修は、生徒と単に通じるための手段以上に、生徒が学びを深めるために不可欠な教師側の言語学習という側面もありますし、「聾学校」の教育職員を対象とした研修体制における重要な構成要素となると考えます。今後も授業の質の向上に向け、継続的に取り組んで参ります。
〒047-0261
北海道小樽市銭函1丁目5番1号
電話:0134-62-2624
FAX:0134-62-2663
メールアドレス:
koutourou-z0@hokkaido-c.ed.jp