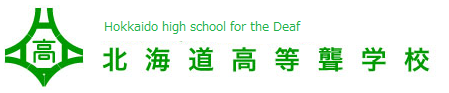今日の高聾
生活情報科のページが更新されました
生活情報科のページが更新されました。
生活情報科のページ からご覧ください。
12月行事予定
「12月行事予定」を公開しました。
行事予定のページ から参照ください。
第36回有島武郎青少年公募絵画展で美術部所属生徒作品が審査員特別賞を受賞
ニセコ町で2024年10月26日から行われる「第36回有島武郎青少年公募絵画展」に本校美術部からも作品を出品しておりましたが、1年生の生徒が制作した作品が「審査員特別賞」を受賞しました。これは、歴代の美術部においても、奨励賞以上の受賞は初となります。
また、その他の1年生から3年生までの部員4名が入選いたしました。
競争率の高い公募展であり、全体に作品の質も非常に高いのが特徴となっていますが、美術部所属生徒が入選のために各人の工夫を凝らしつつ、「自分の表現したいものを表現する」というクリエイティブの本質を失わずに制作を進めてきたこれまでの活動の成果が現前したのだと思います。素晴らしいです。
「第36回有島武郎青少年公募絵画展」は、2024年10月26日(土)~11月10日(日)まで、ニセコ町の有島記念館で行われます。
◎「第36回 有島武郎青少年公募絵画展」特設ページ
https://www.town.niseko.lg.jp/arishima_museum/kikaku/kikaku_2024/10879/
就業体験の事前準備(1学年)
来週から始まる就業体験に向けて、1学年の生徒たちは事前準備を進めています。
インターネットを活用して、実習先の情報や交通手段を確認したり、挨拶の練習をしたりするなど、実習に向けた学習に熱心に取り組んでいました。事前の挨拶に行く前は、「迷惑をかけたらどうしよう」、「コミュニケーションが不安」といった声がありましたが、
実際に訪れてみると「優しそうな人で安心した」、「来週から頑張ろう」という声が聞こえ、生徒たちが意欲的に取り組もうとしている様子が見られました。
生徒一人一人がこの体験を通して成長し、多くのことを学んでくれることを期待しています。
重複学級 校外学習
10月1日(火)に新札幌へ行ってきました。
始めに行った倉式珈琲店では、12月に行うShiawase Cafeに向けて、実際のお店では店員がどのように働いているか見ながらドリンクやデザートを飲食してきました。
青少年科学館では体験活動を通して学習し、理科の授業から出ていた課題のカーリング体験やスケルトン体験、ぐにぐにミラーでの写真撮影などに取り組むことができました。
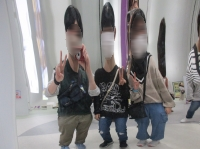

昼食と自主研修をグループで行いました。事前学習で考えた行きたい店や見学したい場所を、予定通りの順番で回ることができました。
帰校後の振り返りでは「初めてプリクラをとりました。」「海鮮丼が美味しかったです。」「サイゼリヤで食べた昼食は美味しかったです。また行きたいです。」「女子四人で仲良く、自主研修をしました。楽しかったです。」という感想が聞かれました。

〒047-0261
北海道小樽市銭函1丁目5番1号
電話:0134-62-2624
FAX:0134-62-2663
メールアドレス:
koutourou-z0@hokkaido-c.ed.jp