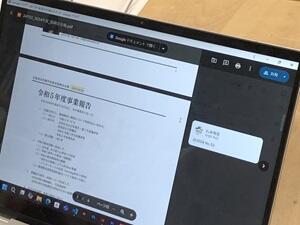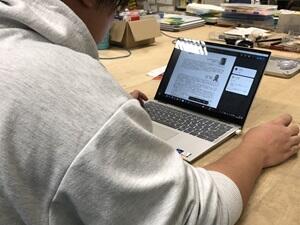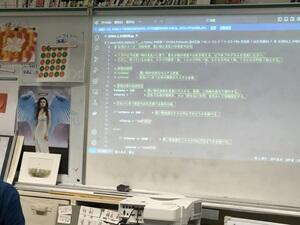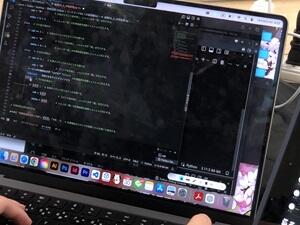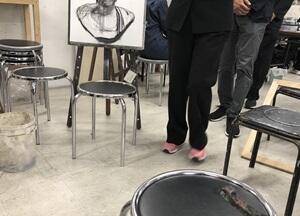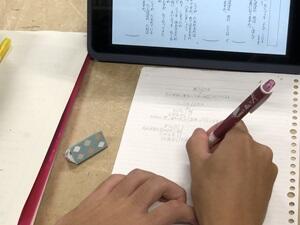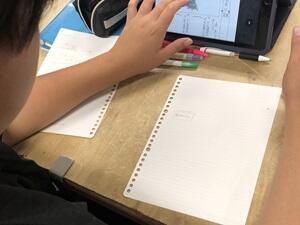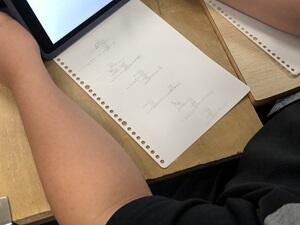活動の紹介・新着情報
スタートアップカンパニープロジェクト_教育振興会会報の制作:情報デザイン科の授業風景
専攻科情報デザイン科では、学生の実践力を育むためにさまざまなプロジェクトを行っています。その中でも特に注目されるのが「スタートアップカンパニープロジェクト」です。このプロジェクトでは、外部からの依頼による出版物等のデータ作成を教材として無償で請け負い、データ作成までの演習を行って、実践的なスキルを身につける機会を提供しています。
現在、取り組んでいる主なプロジェクトの一つは、本校の教育振興会報のデータ作成です。この会報は年末に発行が予定されており、納期が迫っているため、学生は短期間で高品質な成果を求められています。少人数体制で進められていることから、一人一人の負担はそれなりに大きいものの、これらの課題を通じて実社会での働き方や納期遵守の重要性を学ぶ貴重な機会となっています。
制作には、ページデザインの定番ソフトであるAdobe InDesignを使用しています。InDesignは、高機能でそれなりの難易度を有するアプリケーションですが、ページもの制作においては必須のツールです。本校ではこのソフトの使用を通じて、生徒たちがグラフィックデザインの専門スキルを習得できるよう指導しています。また、プロジェクトをOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の一環として位置付け、生徒たちの応用力を高めることを目指しています。
プロジェクトの中では、日本語の和文書体と欧文書体の組み方の違い、文字送りやカーニング、トラッキングの調整方法、段落設定やインデントの効率的な活用法など、組版に関する実践的な技術を学びます。また、Photoshopを使った写真の解像度設定や編集方法なども指導され、総合的なデザインスキルを身につけることができます。
このような活動ベースの授業展開は、上記のようなメリットも多くある半面、時間の制約や教科の系統性を担保する学びとのバランスといった課題があります。納期に間に合わせるためには、時には計画を柔軟に変更する必要もあります。これらの課題をどのように克服するかが、教員側のカリキュラム設計における重要なテーマとなっています。
今後は、教育振興会報の完成後に生徒会誌や学校だよりの制作など、さらに幅広いプロジェクトへの取り組みを予定しています。これらの実践を通じて、学生にはデザインスキルを高めることに加え、チームで協力して仕事を進める能力や、社会で求められる柔軟性を身につけていってほしいと思います。
令和7年度(2025年度)北海道高等聾学校専攻科入学者募集要領について
令和7年度(2025年度)入学者募集要領は、下記のリンクからPDFファイルをダウンロードしていただけます。
適性検査に必要な用具についての説明は、下記のリンクからPDFファイルをダウンロードしていただけます。
適性検査に必要なデザイン用具について(PDF)
出願に必要な書類の送付を御希望の方は、下記金額の切手と、必要な部数を明記したものを同封の上、郵送にて事務局まで御請求ください。必要な部数によって送料が異なります。
1部 180円(速達 480円)
2部~3部 320円(速達 620円)
4部~6部 510円(速達 910円)
7部~10部 750円(速達1150円)
11部以上はお問い合わせください。
「入学案内(入学のしおり)」については、下記のリンクからダウンロードすることができますが、製本された「入学案内」を募集要領とあわせて送付することもできます。その場合の送料は下記のとおりです。
「入学のしおり」付き1部 320円(速達 620円)
「入学のしおり」付き2部~3部 510円(速達 910円)
「入学のしおり」付き4~5部 750円(速達1150円)
6部以上はお問い合わせください。
「入学案内(入学のしおり)」(PDF)
北海道高等聾学校(専攻科)入学選考事務局(担当:堀、桑原)
〒047-0261 北海道小樽市銭函1丁目5番1号
TEL 0134-62-2624(内線58)
FAX 0134-62-2663
北方領土ポスターコンテストで本校在籍生が奨励賞を受賞!
標記の公募に、本校からも応募していましたが、一般の部に専攻科の学生2名、高校生の部に本科生徒1名(2作品)が奨励賞を受賞いたしました。
学習の一環として授業で取り組んできた内容が一定の評価をいただいた結果と受け止めております。ありがとうございました。
Pythonプログラミング:情報デザイン科の授業風景
本校情報デザイン科では、1年生対象の科目「情報技1」において、フロントエンドに係る職業技術の習得のため、幅広くコーディング技術を扱う教育を展開しています。前期は、HTML及びCSSによるコンテンツ制作及びコーディングを中心に学習しましたが、後期からはPythonを取り扱います。Pythonは現在、プログラミング業界で特に注目されているプログラミング言語であり、人工知能(AI)をはじめ、さまざまな分野で活用されています。
授業においては、音声認識アプリを活用するなどしながら、必要な用語を確実に習得できるよう、慎重に情報伝達を行いつつ、指導を展開していきます。
実践的かつ実用的な内容を設定しながら、実際的なプログラミングスキルを身に付けられるよう指導していきます。
プログラミングは、聴覚障がい者にとって今後有力な進路先になりえる職種の一つです。視覚情報を活用することで、コミュニケーションの障壁を超えた仕事に取り組むことが可能ですし、さまざまな分野で活用されるものなので、キャリアの幅を広げる手助けにもなるかもしれません。しかし、その一方で、プログラミングは場面依存性が少なく、法則性のみに基づいて言語を論理的に組み立てる必要があるため、学びの状態によっては最も苦手な分野となりえる可能性も否定できませんす。
そのため、授業においては、丁寧かつ徹底した指導が欠かせません。今年度のPythonの学びは始まったばかりですが、文法事項やプログラミングの基礎をしっかり押さえ、生徒が主体的に学び、実践できるような指導を継続していきたいと考えています。
北海道造形美術学院の授業見学:情報デザイン科の授業風景
9月25日水曜日の校外学習、午後は、北海道造形美術学院様の授業を見学しました。同学院は、美大受験に向けた実技の指導に力を入れている美術予備校で、今回の見学では、私たちの学校で設定されている「デッサン」における作品の質の到達度を確認することが主な目的でした。
まず見学したのは、木大画(木炭紙大の画用紙)サイズのデッサン制作の授業でした。この日は、約15時間程度をかけて、学生の皆さんが構図や陰影、質感を意識しながら作品を仕上げていました。通常、入試における実技科目においては、短時間での完成が求められますが、今回は少し余裕を持った制作時間が与えられていました。このように時間をかけられるのは、作品の完成度を高めるためであり、今後は徐々に制作時間を短縮し、受験に備えた訓練が進められるそうです。
次に見学したのは、油彩画の授業です。この授業では、「円山動物園」をテーマに取材をもとにした作品制作が進められており、油絵や水彩画、粘土作品などを自由に表現する課題が出されていました。学生の皆さんは、各自が捉えた動物や自然の要素を、今後40時間ほどの制作時間をかけて描いていくそうです。
なぜ、今回は時間を長くかけているのかという点について、講師の方からの説明がありました。油彩画は技法的に時間がかかります。しかし、入試では、短ければ6時間程度で仕上げることが要求されることもあり、短時間で作品を仕上げる練習は美大受験には必要不可欠です。ただ、授業においては、最初の段階では、じっくりと時間をかけて試行錯誤し、表現力を深めることが重要だという考えがあるそうです。学生の皆さんは、まだ制作過程の初期段階にあり、技術や発想力をしっかり養うために、あえて長時間をかけて制作に取り組んでいるのです。これは、今後の受験に向けてより高度な技術を習得するための基盤作りとして非常に重要なプロセスなのでしょう。
最後に、私たちの学生との質疑応答の時間が設けられ、特に「質感表現」についての議論が展開されました。金属や木材といった異なる素材の質感を、視覚的にどのように再現するかという質問に対し、講師から「それは表面の問題。金属は見た目でその質感がわかるのは、表面の特徴を視覚的に正確に捉えているから」という具体的なアドバイスをいただきました。本校学生にとっても、質感表現の重要性を学ぶ貴重な機会となりました。
今回の見学で制作されたデッサンや油彩画の作品は、10月13日から19日に開催される「大作画課題展示」展で公開予定だそうです。学生の皆さんがどのような方向で作品制作を展開、完成させたのか、その成果を見ることができるのが楽しみです。
例年同様、学生の皆さんの技術力と制作に向かう心構えを改めて目の当たりにし、非常に刺激的な時間となりました。あらためて、このような機会をいただいた北海道造形美術学院様に改めて感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。
ペーパーショップサクマ見学及び紙に係る専門講習:情報デザイン科の授業風景
専攻科情報デザイン科では、校内の施設設備では十分に学びを展開することが難しい事柄について、近郊の施設等のリソースを活用すべく、校外学習を行っています。
9月25日水曜日の校外学習においては、今回は、500m美術館やほほえみカフェなど、札幌市内中心部を中心に見学等を行いました。
午前中の中心的活動は、ペーパーショップサクマ様における店内見学と紙に係る専門的内容のレクチャーです
営業時間内の店内での活動となりますから、サクマ様には大変御負担と御無理をおかけしたかと存じますが、それでも快く受け入れていただきましたことに、改めて心より感謝申し上げたいと思います。
見学においては、まず、担当係長様から、紙製品を扱う店舗での説明をいただき、店の歴史や商品の概要が紹介されました。札幌市内で60年以上続くこの店舗は、主に印刷用紙の販売を行っており、一般向けにも少量の紙を提供している点が特徴です。紙の種類については、コピー用紙やトイレットペーパーといった一般的な紙から、特殊な印刷用紙まで幅広く取り扱っていますが、この店舗では印刷用紙を中心に扱っているそうです。大きなサイズの紙を切り分けるサービスも提供しており、希望に応じてカスタマイズすることが可能です。
続いて、紙の厚みやサイズに関する説明があり、紙の厚さを「キロ」で表現する「連量」という独特の方法が紹介されました。この方法では、紙1000枚の重さで紙の厚さが表され、70キロや135キロといった数値がその紙の特徴を示します。また、紙の厚さを測る機械が実演され、具体的な数値で紙の特性が示される場面がありました。この説明を通して、紙の選定が単なる厚さや大きさだけでなく、用途や希望に合わせた精密な調整が必要であることが理解されました。
さらに、紙の「流れ目」についての説明が行われました。これは印刷や製本時に非常に重要な要素であると強調されました。紙の繊維がどの方向に流れているかによって、折りやすさや仕上がりが異なります。この知識がないと、製品の品質が大きく左右されるため、印刷業者やデザイナーにとっては重要な情報です。
倉庫見学では、巨大な紙がどのように保管されているかが説明され、湿度管理などの細やかな配慮が必要であることが説明されました。特に見どころは、倉庫内の断裁機の操作方法のデモンストレーションです。紙の裁断に精密な作業が求められる様子が紹介されました。この機械は非常に古いそうですが、それでも一度に大量の紙を正確にカットすることができ、長年使用されていることから、その信頼性が感じられました。紙をカットする際の圧力調整やズレを防ぐ仕組みなど、細かい技術的な説明もあり、美しい仕上がりにおける断裁の重要性がよく伝わりました。
最後に、店内の特殊紙の展示を見学する時間が設けられました。店内は、色や模様、手触りが異なる紙が多数展示されており、デザイナーやクリエイターにとって魅力的な選択肢が豊富に揃っています。SDGsに配慮した製品として、野菜の繊維を使った紙や、環境に優しい素材が使われた製品も紹介され、現代のトレンドに沿った商品開発が行われている様子が伺われました。また、商品に実際に触れさせて頂く機会もいただき、学生は実際に紙に触れ、凹凸や厚さを確認しながら、紙の多様性を体感することができました。
紙の知識は、グラフィックデザインにおいては、設計の土台として極めて重要な要素です。このことについて特に取り出して学習する機会を得たことは、非常に有意義なことと考えます。このような機会をいただいたペーパーショップサクマ様に改めて感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。
SLAの知見を生かした日本語指導と編集工学的アプローチ:情報デザイン科の授業風景
専攻科情報デザイン科の現代文の授業では、SLA(第二言語習得理論)の知見を活かし、日本語の文法や表現を深く理解するための「アクティブラーニング」を取り入れています。この授業の特徴は、単に文法を学ぶだけでなく、情報デザインに不可欠な「情報の整理能力」を磨く点にあります。主要科目であるグラフィックデザインにおいても、情報の整理と表現は重要なスキルであり、この授業はデザインと日本語指導を一体的に学ぶことで、その力を効率的に高めることを目指しています。
デザインとは、結局のところ「情報の整理」です。視覚的な要素を効果的に配置し、メッセージを明確に伝えるには、情報をどのように整理し、伝えるかが鍵となります。ここで重要になるのが編集工学の視点です。編集工学では、情報をフレーム化し、その構造を明確にする手法を学びます。このスキルは、日本語の文型と一体的に学んでいくことがポイントとなります。文法を整理し、適切なフレームとして活用することで、複雑な情報をシンプルかつ効果的に伝える力が育まれます。
さらに、授業では日本語文法の図像化や語義モデリング言語を使った語義の構造化、「言い換え」や「比喩」を使った学習などを通じて、思考を抽象化し、多角的に物事を捉える力を育てます。たとえば、具体的な事象を抽象的な概念に結びつけることは、デザインでも言語活動でも共通のスキルです。これにより、学生は単に表現技法を習得するだけでなく、視覚的情報と言語的情報の両方を効果的に整理し、伝える力を養います。
また、「アブダクション(推測)」もアクティブラーニングを進める上で重要な要素です。限られた情報から合理的な結論を導き出すプロセスは、デザインにおいても言語活動においても同様に求められます。文型を一部から推測し、全体像を掴む力は、デザインの場でも役立つスキルです。たとえば、視覚的な要素の一部から全体のコンセプトを推測し、デザインを完成させる能力に通じるようにです。
専攻科情報デザイン科の現代文の授業では、日本語指導と情報デザインのスキルを同時に学び、SLA理論や編集工学のアプローチを通じて、情報の整理・編集を体系的に身に付けていきます。これにより、学生はデザインにおける表現力だけでなく、言語を使った情報の整理や発信力にも応用されていくことになります。
遠隔通信の制限的利用による校内イベントのオンライン参加:情報デザイン科の授業風景
先日、校内で卒業生をお招きした講話がありましたが、その際、専攻科では授業の一環並びに今後の行事の効率的な運用の実験的な意味合いも含め、ビデオ会議システムや動画のストリーム配信の限定公開等による校内オンライン形式での授業参加に取り組みました。
これまでも、このような本科との合同の講演形式の授業においては、オンライン形式での授業に係る試験的運用を行ってきており、カメラの位置や角度、焦点をあわせるべき対象などを吟味しながら、より見やすい映像、また参加しやすい形式を追求するなど、改善を重ねて参りました。このようなテレコミュニケーションによる授業参加は、持続可能性の追求と遠隔学習の学び方の理解という観点で、今後重要な指導形態になっていくように感じますし、今後より一層の活用の幅を広げていくべく、研究を進めてまいりたいと思います。
専攻科情報デザイン科在籍学生の制作した作品が「新道展」に入選しました
専攻科情報デザイン科在籍学生が制作した作品が新北海道美術協会が主催する公募展「新道展」に入選したしました。快挙です!
この作品は、銭函の海で見つけたさまざまなオブジェクトを利用し、学生生活を送る「今」を表現しているそうです。
このオブジェクトの配置における位置関係は、自身が継続して取り組んでいるバイオリンの演奏曲がモチーフとなっており、
個性豊かなインスタレーション作品に仕上がっています。
作品の展示は、札幌市民ギャラリーで9月8日日曜日まで行われています。
高聾祭ディスプレイ2024(4):情報デザイン科の授業風景
グラフィカルなデザイン制作において、レイアウトに係る法則性は極めて重要です。基本的には、大きく2つの方向性があるわけですが、一つは対比のバランスを極めるもの、もう一つは細分化された要素を集合させる手法になります。
1階から4階に至る階段の壁面に展示されたインスタレーションは、上記の後者の手法のお手本とも言える作品といえるかもしれません。
単純な幾何形体の繰り返しではありますが、色相のグラデーションという配色パターンの法則性が作品全体のフレームを構成し、かつ、アクセント的に付け加えられるイレギュラーな配置が、造形的な価値と創造性をほどよく補っています。