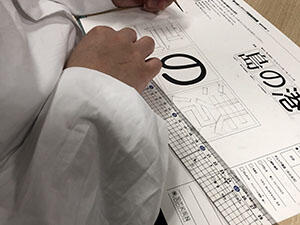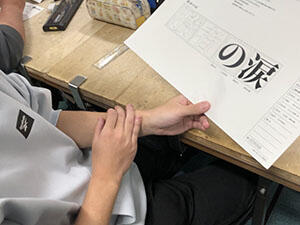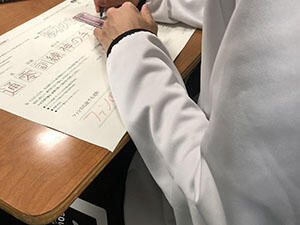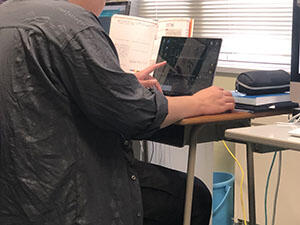2024年6月の記事一覧
写真とろう者:情報デザイン科の授業風景
写真は、ろう者にとっての芸術表現の手法において、最も馴染み深いものの一つであり、視覚的な認知特性にあった活動となりやすい題材の一つです。
一眼レフカメラを利用した撮影は、すべての情報デザイン科の科目の中の活動の一部としてとりあげられますが、ここでは「シャッタースピード」と「絞り」の関係から導き出される「露出」の概念の理解が非常に重要となります。
このあたりを理屈ではなく、活動ベースで学び、そこから得られる結果を学びの内容として概念化していく。ろう者の学びにおいて、そのような展開が期待できる非常に効果的な題材の一つであり、さらに、「大好き!」という学生も多いです。やはり、それは彼らの視覚的な認知特性に合ったものだからと考えますが、そこから後加工の領域に拡げたり、グラフィックデザインのレイアウト技法に拡げたりと、展開の幅も広く、聾学校で商業デザインを扱う学科としては、やはり必須の内容かと考えています。
レタリングについての一考察:情報デザイン科の授業風景
レタリングは、以前は職業技術として専攻科情報デザイン科のカリキュラムとして技術指導が重視されていた内容ですが、現在は、DTPによるデータ作成と大判プロッタでの出力が主流となり、現実的にはあまり頻繁にはもちいられない技術となりました。
ただ、検定試験の内容などは、明らかに現代のDTPやWebのフォントの仕組みを意識した内容になっていますし、知識問題の内容も、グラフィックデザインに関するベーシックな知識を問うものが多く、系統立てた学習を進めるうえで有意義なものになっています。加えて、領域としての自立活動として教科指導の中に組み込まれる日本語指導において、ここで用いられる文型は、意味の階層性を示す文型としてオーソドックスなものであり、構造と日本語文の間を行き来する思考の深化のための学びを兼ねた学習教材として有効なものであると考えています。
ICTを活用した授業展開:情報デザイン科の授業風景
専攻科情報デザイン科では、ICTを活用した授業を積極的に取り入れていますが、ここ数年、社会全体でその動きが加速化しているように感じます。
教育の情報化というよりは、それを超えたポスト情報社会、いわゆるSociety5.0の社会の在り方を反映した授業ともいうべきでしょうか。
ゼロから作るのではなく、コンテンツを利用する、素材を組み合わせる、といったことがあたりまえの授業になってきたように感じます。それは、ゼロから何かを生み出すクリエィティブではなく、組み合わせることで価値を生み出すクリエイティブとも換言できるのかもしれません。コーディネートの力、ひいては、それがデザインの力に直結していくものと考えます。
学生の多様性に対応した内容の精選や手立ての工夫を講じつつ、フレーム自体は変わらない。その理念は、情報デザイン科の唯一無二の特性として貫き通していきたいと考えています。
令和6年度がスタートし、2ヶ月が経過しました:情報デザイン科の授業から
令和6年度がスタートし、早いものでもう6月です。
専攻科情報デザイン科では、今年度新たに4名の学生を迎えスタートしました。
ここでの学びでは、もちろん造形活動そのものに焦点を当てた学習活動が中心とはなるのですが、その体験を経験に昇華し、知識として他に応用していくためには、ひとえに言語の力が必要になってきます。
これまでにも御紹介しているとおり、さまざま授業の中で、いわゆる領域としての自立活動として、視覚化された日本語の文法要素を利用した内容と文法の一体的な活動を進めています。
今回取り上げた色彩構成は、特に色という抽象的な要素を扱う科目であり、また、色の関係性や配色イメージなどいった不可視な要素も多くなりますので、学びの在り方として特に重要なものになってくると思われます。
約2ヶ月の学びにおいて、赤、青、緑の上位概念はRGB、光や色料で分ける色の分類という観点で、RGBと並列するのは?CMYKです。というようなやり取りができるようになってきており、このあたりの静的構造の操作を通した言語と思考の比喩の往来が「思考の深化」の鍵を握っているものと考えています。